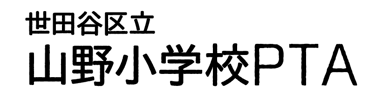10月29日(土)、山野小の多目的室にて『楽しく学んで行動しよう!プログラミングで海のSDGs!』というイベントが開催されました。
イベントは、一般社団法人イエロー ピン プロジェクト・日本財団『海と日本プロジェクト』共催(協力:山野小PTA)で行われました。
この記事では、3~6年生(参加に応募いただいた約40名)を対象にしたワークショップ(SDGs×Scratchプログラミング)の様子についてお伝えします。
※1~2年生対象のワークショップ(粘土工作×Scratchプログラミング)については、こちらの記事をご覧ください。
午前中に行われた1~2年生のワークショップとは雰囲気が変わり、午後の部は学習色が濃いワークショップとなりました。
プログラミングを教えてくれる先生の説明はとても分かりやすく、質問もしやすい環境を作ってくれたので、子どもたちは熱心に説明を聞いて、考えて、分からないことはきちんと質問していました。
プログラミングを使って、おなかをすかせたシャチを魚がいる場所に移動させ、魚を食べさせます。シャチは魚を食べるとエネルギーが補給でき、動き続けることができるのですが、、、。
ここで、先生が「何か気付いたことはありませんか?」と子どもたちに質問します。
すぐに気付いた子もいれば、何度もプログラミングを実行させてシャチの動きをじっくり確認している子もいます。
7匹いる魚のうち、ある2匹は、食べてもシャチのエネルギーになっていなかったのです。
この2匹、実は魚ではなく海洋プラスチックゴミでした。シャチは、ゴミも魚だと思って食べてしまうのです。
そこで、プログラミングで「魚を食べる」の定義に「もし」を追加します。
定義:魚を食べる
もし、魚A(本物の魚)に触れたなら、
食べる を送って待つ
このプログラミングを実行すると、シャチは本物の魚だけを食べ、2匹の魚(海洋ゴミ)を残し、エネルギーは満タンになりました。
これで、めでたしめでたし、、、?
答えは「いいえ」ですね。
現実世界では、海の生き物に「本物の魚だけを食べて」というメッセージは送れないよね(たぶん)、という流れでクイズ形式での座学も行われました。
子どもたちは、各自プリントにクイズの答えを書き込んで、最後まで真剣に取り組んでいました。
また、大阪の高校生が開発したレジ袋の話や、鹿児島の小学生が海で拾ったマイクロプラスチックを瓶に詰めて販売している話も紹介されました。
「今、自分ができることを考える」や「プログラミングを使うと、社会に対してできることが増える」というキーワードが、少しでも子どもたちの中に残ってくれていたら良いなと思います。
120分という長い時間、子どもたちは本当にお疲れ様でした!!
広報担当












PTAについて、もっとこんなことを知りたい!という点があれば、お気軽にお問い合わせください!