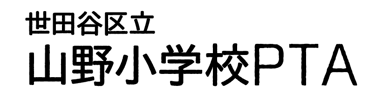【家庭教育学級講演会】「親子で学ぶ 性教育」
2023 年 11 月 25 日、山野小で家庭教育学級講演会「親子で学ぶ 性教育」を開催いたしました。
昔に比べ子どもの成長が早くなった今、「性」について親子で話してみるきっかけができたらという想いから選んだテーマです。講師は看護師、保健師、養護教諭の資格を持ち、山野小の保護者でもある齋藤恵美さんです。
開催にあたり事前にアンケートで質問を募ったところ、
「どうやって伝えたら、話したらよいのか?」
「危険から身を守るにはどうしたらよいのか?」
「インターネットから情報を得てしまうのが恐い」
などなど皆さん同じような悩みを持っていることがわかり、講演はご質問に応えるかたちで進められました。
<講演内容>
リプロダクティブヘルスライツについて/ 海外と日本の性教育の違い/ 性教育とは?/プライベートゾーンって?/ 世界共通の SOS ハンドサインと事例/ 男の子の体・女の子の体、洗い方/ 射精/ 生理・月経前症候群・月経困難症/ 成長の平均(男女差)/HPV ワクチン/ 性感染症/ 中学生になるみなさんへ/ Q&A スマホ対策、話し方
盛りだくさんの内容となりましたが、質問や反響の多かったお話しをいくつか紹介します。
★「性教育」とは「生教育」。
性教育と聞くと、子孫を残す生殖ばかりが扱われるイメージですが性教育とは、生きるための教育・知識です。生きることそのものです。
どう生きて、どう死にたいか、人生すべてを通しての考え方です。
① 自分はどう生まれたのか=自分とは何か (自我の確立、自己肯定)
② 自分の体や心を知る=どう生きていくのか (健康管理)
③ 共に生きるために=自分も他者受容する心、NO と言える自分に
(防犯意識、共生)
★世界共通の SOS ハンドサインと事例

このサインは声が出せない時にまわりに SOS を知らせることのできる世界共通の助けてのサインです。日本でも誘拐されそうになった時に、通りすがりの人にこのサインを見せて助かった事例もあったそうです。
1、手のひらを見せる
2、親指を曲げる
3、残りの指も曲げる
4,開いたり閉じたりを繰り返す。
講演では「わるい人」に連れ去れそうになった「えみちゃん」がこのたすけ手サインをしたところ、気づいてくれた見知らぬ「よい人」が声をかけたことによって『わるい人』が逃げて行きました。
★ Q; 親から性的な話題をするのが恥ずかしいです。
もし子供から質問があったらどう伝えたらよいか教えてください。
A; まず「よい質問だね。どうしてそう思ったの?何かあったの?」と答え
ましょう。
その先の大事なポイントは 3 つあります。
① 汚い、下品という反応はダメ
② はぐらかさない。茶化さない。怒らない。真剣に向き合うこのチャンスを逃すと親も子も性的な話題はタブーになってしまう。
③ 主観ではなく科学的根拠や理由を説明する。
講演の終盤では打ち解けた雰囲気の中、参加者の質問に直接齋藤さんが回答しました。
親子でのご参加をおすすめしたこともあり、当日は 4 割ほどがお子さんの参加でした。
保護者がゆっくり講演を聞けるようキッズスペースを設けました。
保健室や病院からお借りした赤ちゃんや女の子のお人形、参考文献や生理用品なども展示されました。講演後は赤ちゃんの重さを懐かしむように抱っこする保護者や、おんぶしてかわいがったり体を観察する子供たちが周りを囲みました。
この講習会は家族が参加した委員の我が家にとっても性教育の入り口となりました。
ハードルが下がり構えなくても性教育的な話が少しずつできるようになった気がします。
講師の齋藤さんより
沢山の方に参加いただき関心の高さを感じました。毎年開催してほしい、子供にも教えてほしいとのお声を複数頂き嬉しく思います。また機会がありましたら、ご意見を元にさらに良い講演会できるよう研究も続けていきたいと思います。
家庭教育委員会サポーター